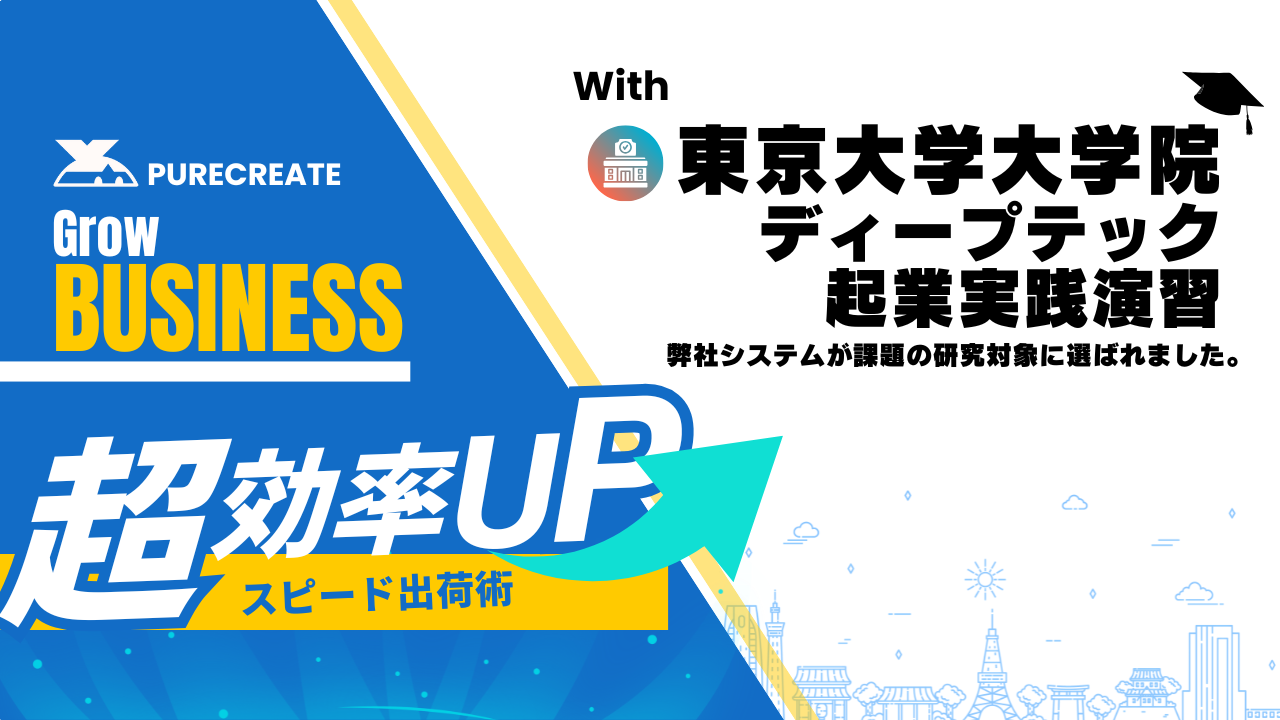今後の物流システムにどんな影響を与えるのか?
現場オペレーションを握る企業と、東京大学というナレッジが組んでいくことで、 どんなシナジーが生まれるのか─この動きは、その試金石になる。
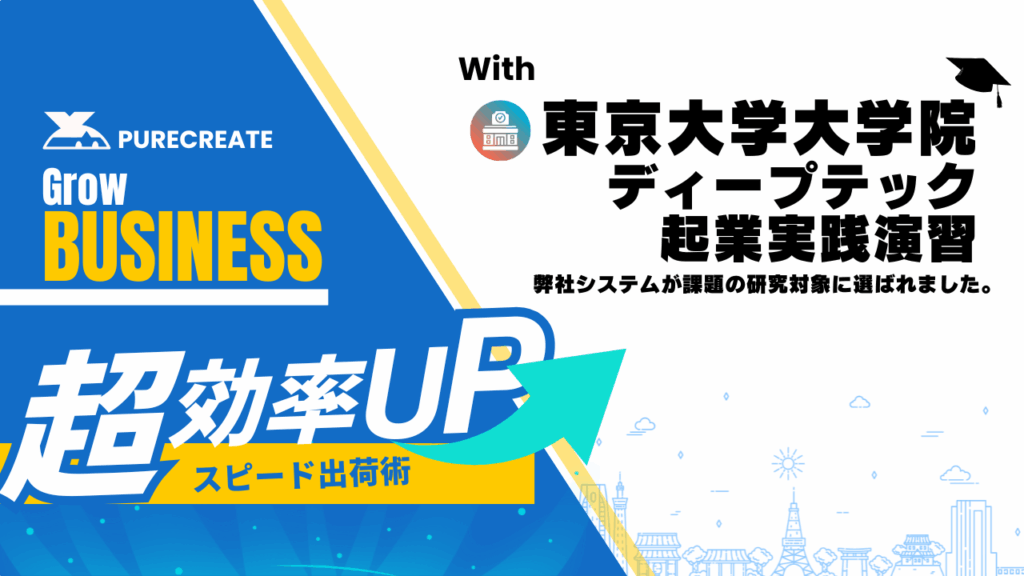
問い|いま起きているのは「出荷の効率化」ではなく、産業インフラの再設計では?
月間6万件を超える出荷をさばくEC事業者ピュアクリエイト(本社:埼玉県熊谷市)が、 自社の物流オペレーションと独自システムを東京大学大学院・山川研究室に提供し、研究協力を始めた。 対象は、コスメや日用品、ファッション雑貨、おもちゃといった「柔らかく、形もサイズもまちまち」な商品を、 人ではなくロボットにどう扱わせるかという領域。
これは、単なるEC企業の改善ではない。倉庫という“現場の知恵”と、大学という“知の装置”が 直接つながることで、次世代の物流オートメーションの姿そのものが組み替えられようとしている。
この動きは、大手フルフィルメント企業や巨大モールだけがロボット化を進める…という これまでの構図を崩す可能性がある。むしろ、日本の中堅ECプレイヤーや地域拠点レベルの倉庫現場が、 研究の起点になりはじめたということだ。
ここに、「物流」という言葉の定義変更の予感がある。
現場|“柔らかいモノ”をどう秒速で出荷するか、という未解決課題
ピュアクリエイトは、美容・家電・日用品など多ジャンルの商品を扱うECを運営し、 月間最大60,000件超というボリュームを、高速かつ正確に出荷している。
この現場オペレーションには、いくつか本質的な難しさがある。
- 商品の形や硬さがバラバラ(化粧水ボトル、コード類、パッケージの柔らかいお菓子、ぬいぐるみ…)。
つまり、ロボットアームにとって“つかみにくいもの”ばかり。 - SKUの回転が速い=学習済みの定型動作だけでは対応できない。
- 梱包~封緘~送り状貼りまでを止めずに流す必要がある。
ピュアクリエイトでは、流れてきた商品を箱に入れてバーコードを読むだけで、 封を閉じてラベルを貼るところまで自動でつながるラインを構築している。
これは、ロボティクス研究側にとって“最高の教材”になる。 研究室の中では再現しづらい「リアルな不揃い」「ヒューマンエラーまで含んだ実態」「秒単位の処理圧」が、 まるごと観測できるからだ。
今回、東京大学大学院では「柔軟物の高速画像解析」と 「ロボットマニピュレーション(つかむ・持つ・詰める動作)の応用」をテーマに、 “やわらかいモノを機械に扱わせる”ための実装研究を進めている。 その実験フィールドとして、ピュアクリエイトの倉庫オペレーションが選ばれた。
これは重要だ。
研究側は「世の中で本当に必要になるロボットの仕事」を、机上ではなく本番環境で検証できる。
企業側は「うちのオペレーションを、どう分解すれば機械が再現できるのか」という視点を手に入れる。
この往復が、そのまま“物流DXの設計図”になる。
なにが変わる?|人手不足の穴を埋めるロボット、ではもう足りない
いま、日本の物流業界は「人手が足りないから自動化したい」という文脈で語られることが多い。
でも今回の動きは少し違う。
ピュアクリエイトは、研究チームを倉庫に呼び、 ピッキングから梱包、出荷に至るまでの実オペを公開し、 改善サイクルや“現場目線の課題”をそのまま共有している。
つまり「どこをロボットに置き換えるか」ではなく 「どこをロボット前提で再設計すべきか」という会話にしている。
この視点転換は、将来の物流システムに3つの影響を与える。
- 個別最適から“ラインとしての最適”へ
いままでは、ピッキング用ロボット、梱包用マシン、ラベラー…と装置単位で語られてきた。
これからは「一人のスタッフがバーコードを読むだけで、 箱閉め〜送り状貼りまで一気通貫で自動に流れる」ような、 “人+機械の合奏”設計が標準化されていく。
これは、現場ごとにカスタムするコストを下げ、 中小~中堅ECにも導入できるレベルまで自動化ノウハウを落としていく動きにつながる。 - “不揃いな商品”を扱えること自体が、競争力になる
アパレル、コスメ、日用品、ベビー用品、家電アクセサリーなど、 サイズも硬さも安定しないSKU群を高速にさばけるなら、 それはもはや単なる倉庫オペではなく 「マルチカテゴリ対応型の物流OS」になる。
こういう“柔らかいモノ前提の自動化”が一般化すると、 カテゴリがバラけているECやD2Cブランドでもスケールしやすくなる。 - 地方発×大学発の共同研究モデルがスタンダードになる
今回の主役は、巨大資本のメガ倉庫ではない。
埼玉県熊谷市に拠点を置く企業と、東京大学大学院が直接結びついたケースだ。
これは、地域物流拠点が“研究インフラ”になるモデルでもある。
もしこの形が増えれば、「最新ロボティクスは首都圏のラボから降りてくるもの」 という一方向の構造は崩れる。
現場の改善知が、そのまま産業技術の一次データになる。
シナジー|東大という“知の装置”が入る意味
東京大学側の狙いは、ディープテック起業(研究から事業を起こすこと)まで見据えた 実装研究にある。これは、ただ論文を書くための共同調査ではない。
研究テーマ自体が「社会でどう流通するか」まで想定されているということだ。
この設計思想は、ピュアクリエイトにとってもメリットが大きい。
- 自社の改善ノウハウ=暗黙知を、研究の言葉で形式知化できる。
→ 将来の内製システムの高度化、人材採用・教育の標準カリキュラム化に直結する - “東大発”という信頼性は、取引先やサプライヤー、ひいては金融機関や自治体に対する説得力にもなる
- 「現場の当たり前」を社会的な技術課題として提示できることで、 物流=単なるコストセンターという扱いから抜け出しやすい
もう一つ見逃せないのは、企業側がこの取り組みを “社会貢献の一環”と明言している点だ。
研究を囲い込むのではなく「業界全体の効率化」にも役立てたいというスタンス。
物流・EC領域の“現場知”を共有資産にしていくことで、 国内サプライチェーン全体をアップデートするというメッセージがにじむ。
これから|ラストワンマイルの前に、“ラスト1メートル”の争いになる
これまで物流の議論は「ラストワンマイル(お客さんの玄関までどう届けるか)」に集中してきた。
でも、人口減少・人手不足・小口多品種という日本のEC構造を考えると、 本当のボトルネックはむしろ倉庫の中の“ラスト1メートル”かもしれない。
ピッキング→箱詰め→封緘→送り状貼付。
この一連の流れを、人とロボットの最適な分担でいかに秒単位まで磨くか。
それができる事業者は、同じ在庫量でも回転スピードで勝てる。
返品・交換対応のスピードでも勝てる。
つまり「物流」がそのまま「ブランド価値」になっていく。
ピュアクリエイトと東京大学の連携は、その“1メートル”の標準仕様を つくろうとしているように見える。
倉庫の床が、次世代ロボティクスの実験台になる。
そしてその仕様が、地域のEC、中小メーカー、D2Cブランドにまで降りていく。
これはもう、ただの倉庫改善ではない。
日本のEC競争力そのものを底上げするインフラづくりの第一歩だと、 NEOTERRAINは見ている。
出典・参考
本記事は、ピュアクリエイト株式会社が東京大学大学院 山川研究室と連携し、 月間6万件超の出荷オペレーションおよび独自システムを研究対象として提供したことを発表した 2025年10月25日公開のプレスリリース 「EC通販の舞台裏、ついに東大の研究対象に ─ ピュアクリエイト、月間6万件超えの出荷を支える独自システムを東京大学大学院の研究に提供」 (PR TIMES掲載)に基づき再構成しています。